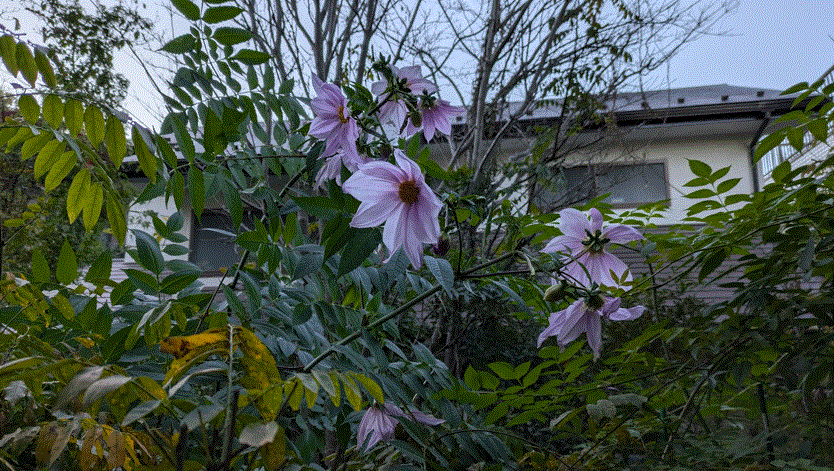「どれぐらいの期間で3級ぐらいに合格しますか?」という質問をうけることがよくあります。そろばんを習う上でのひとつの目標ですね。 週何回習うか、いつ(何歳)から習うか、掛け算九九をを覚えているかなどの条件で大きく変わるテーマですので、本来は、単純に答えられる質問ではないのですが、当教室の場合には現在の全員の実績からほぼということで答えています。
実際のところ、当教室は週2回制ですので、週3回やほぼ毎日学習しているところには昇級スピードはかなわないところもあります。 しかし、習い事をいろいろやりたい時代にそろばんだけに時間を使うことはなかなか難しいこともあり、ゴールを現実的におさえています。 要は、最低この程度の技能として習得できていれば、そろばんを学習した意味があるのではないかと考えたところに置いています。しかし、相応のレベルまでは頑張れば到達しています。
そろばんの技能を極めたいとなれば毎日何時間も訓練することが必要ですが、そこまで希望すればそれば個別に対応ですね。 それよりも全員を対象で、そろばんは、週2回でもしっかり学習することで、一定の級に合格し日常で使うことができ、競技会にも参加でき楽しめる、そういう形のゴールの方が好ましいのではと思っているからです。
習い事を考えるときに、どういう能力をいつぐらいまでに習得したいかも全体時間のやりくりの中で到達レベル目標をお考えいただければと思います。