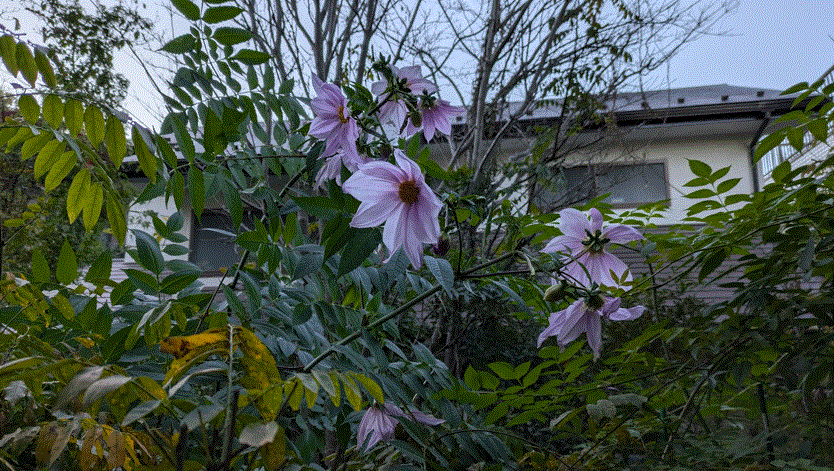給食も始まり、6時間授業もで、ようやく学校も普通になってきたようですね。長いお休みから以前の形に戻ったところに暑さも加わり、そろばんに来た時には、疲れてしまっている姿も見られます。まずは、慣らし運転かもですね。継続学習してきた人はそのまま加速し、リハビリが必要な人は、1ヶ月で取り戻すことですね。教室は特に変わらずで、その時々のテーマに向けて訓練・鍛錬をすることに注力です。コツコツとやることが大事ですが、苦手であっても諦めずですね。日々の練習は必ず身についていきます。
ところで、いろいろなスポーツも始まりました。でも「無観客試合、リモートマッチ・・・」、TVを見ていつも楽しんでいる人は大差はないかもしれませんが、実際の選手は物足りなさがあるように見えますね。「できないよりはまし」といっている選手もどこか寂しそうです。また、演芸バラエティ番組「笑点」を見ていても全員がリモート参加。「笑い」に違和感を感じますね。集まった会食時に「無言で黙々と食べるだけ」というのも同様ですね。やはり、なんでもというのは無理があるように思われますね。単純にその状態に慣れていないということではなく、目的との違いに「共感できない」という感覚は多くの人が感じていることかもしれませんね。これまで通りができないならば、新しいものにとってかわった方がよいのでしょうかね。残念ですね。
一方で、そろばん学習に対する「共感度」について考える機会も続いています。こちらは、そろばんをやってみるかどうかの共感の感覚ですね。今年は、世の中は大変な状況だったのですが、例年以上の問い合わせがありました。実際に話を聞き、そろばん学習に対する共感度が高まれば、習い事の1つとしての選択肢になります。そもそもそろばん学習を知らない人がたくさんのことがネックかもですね。共感できなければほかの習い事を選んでいただいて構わないですが、年初から、今月、来月にも入学者が続いています。あとは、途中の停滞があったとしても、数年間しかっかりと頑張って、卒業するときに武器になる技能が身についていればですね。