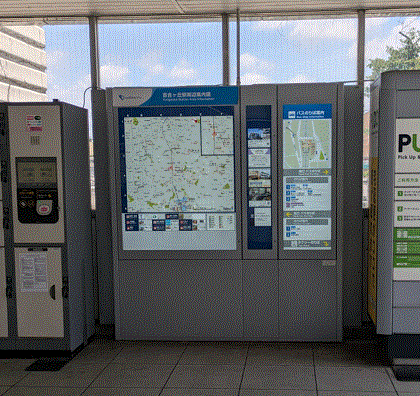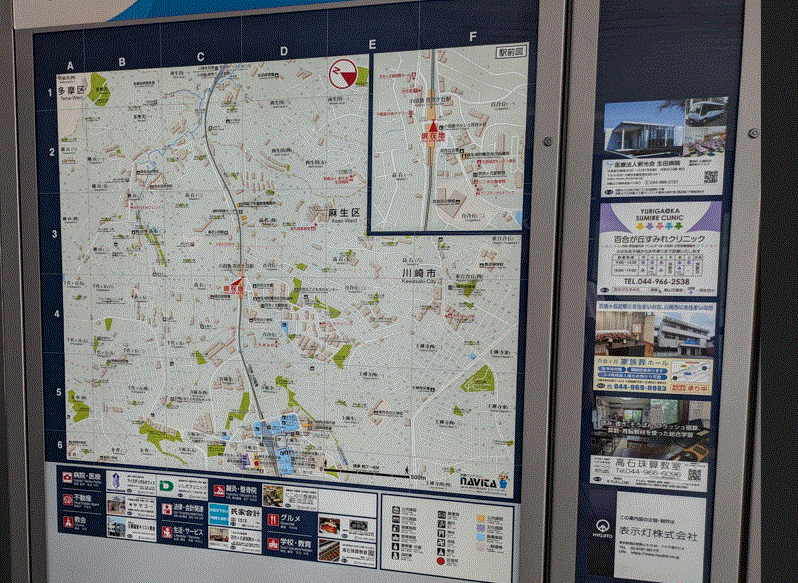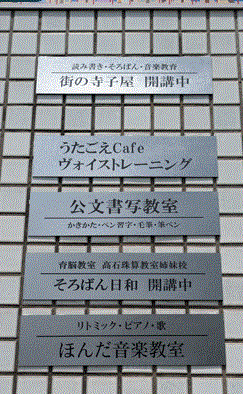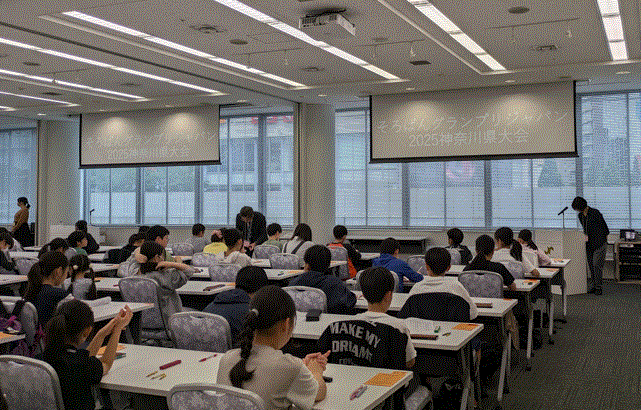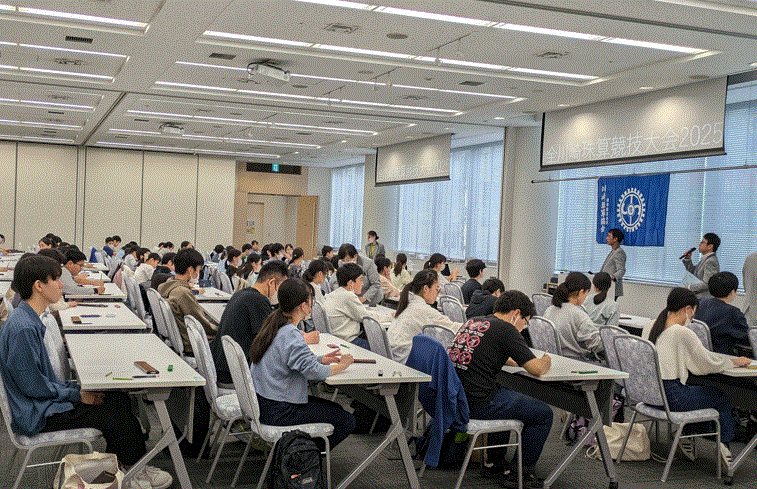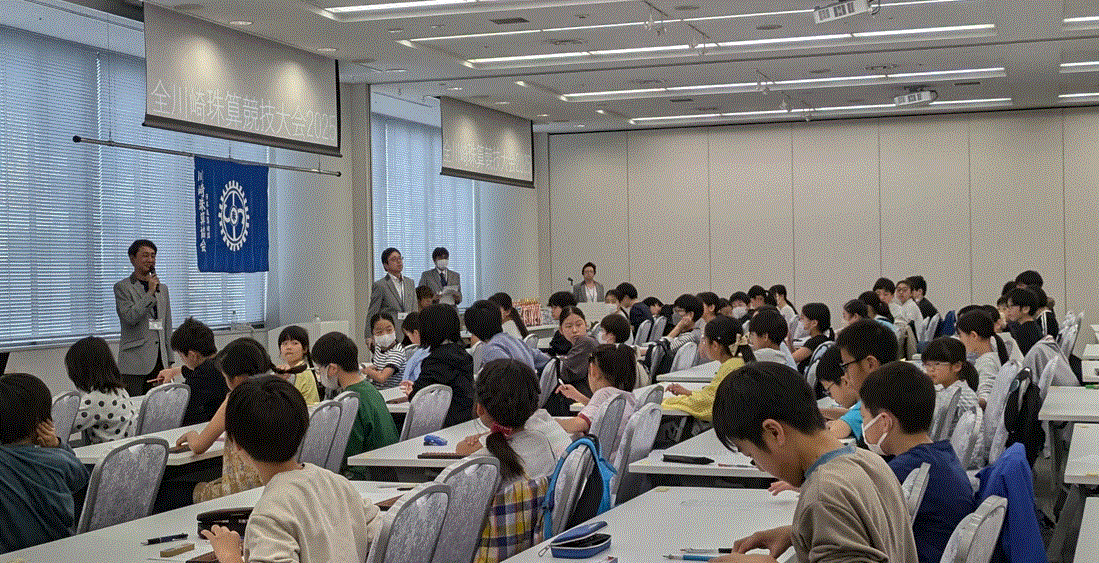先週実施の8月の教場検定の結果をボードに貼り出しました。夏休み、夏休み明けの検定試験でしたので受験者は少なかったですが、3種目同時合格者1人を含む、全体的には良い結果だったとは思います。ただ、読上、読上暗算の上級はやはり今回もとても難しかったですね。
「 珠算 」は、前回の6月にたくさんの合格者で少ない受験者の7人受験でしたが、6人合格。珠算準1級の2人は本番で9割以上の得点のとても良い結果がだせました。初めて受験の9・10級受験の2年生の男の子と女の子の2人もとても良い成績で9級に合格です。試験前はソワソワしていましたが、結果がだせてよかったですね。 「 暗算 」は、2級の受験者2人と5級で1人が合格点に届きませんでしたが、11人受験で他は8人が合格です。暗算1級の2人は姉と弟の同時合格ができました。レベル的に難しい暗算1級の兄弟姉妹での同時合格は、教室でははじめてと思います。 「読上算」は、1級、2級がそれぞれ2人合格。3級以下は、10人受験で半分の5人合格。普段の練習不足の感のある人はやはり届きませんね。読上算1級はなかなか合格点がとれなかった2人がようやくクリアです。よかったです。さらに、1人は難しい読上算1級にもかかわず、満点合格です。合格点に届かなかったほかの3人のメンバーもあと少しでしたので、次回にリベンジです。なお、以前に1級合格で今回読上の段位検定に挑戦の1人は、準参段に認定です。これも素晴らしいですね。 「読上暗算」は、残念ながら1級は届かず、2級、3級も各1人。全体でも4人の合格でした。1級はなかなかハードルが高いですね。5級、6級はリベンジ組がクリアです。
今回の検定結果で2人が5種2級以上合格に到達できました。ほかのメンバーも順番に積み上げています。あと1つか、2つの人は、3月の表彰式に向けて、10月と12月の検定試験であと何人が到達できるかですね。頑張りましょう。