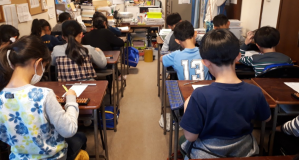今回の2月の検定は教場検定と試験場検定あわせて珠算に全体の6割を超える受験者でした。2ヶ月ごとに検定試験で技術レベルを確認できるのは技能習得の習い事としては優れている一つと言えますね。週2回の学習ですが、結果は以下の通り良い結果でした。。
今日発表の教場検定結果は、珠算、暗算は、インフルエンザの欠席者を除くとほぼ8割のとても高い合格率で、読上種目の読上算、読上暗算は、全体でほぼ5割の合格率でした。教室全体としては、12月検定に続きとても良い結果でした。珠算・暗算の昇級者はまた一つ上のレベルに挑戦していくことができます。どちらにしても、今回は一人一人とても頑張った結果だったと思います。数名の届かなかったメンバーは次回にリベンジです。
たくさんの珠算受験者の中では、初受験の1年生の男の子2人は珠算も、読上暗算も合格です。最後までよく頑張り、結果を出しました。良い経験だったと思います。もう一人の初受験の3年生は、珠算7級、暗算6級、読上暗算6級に入学4ヶ月目でしたが合格しました。12月と続いて2回目の受験の学習期間5か月目の年長さん、1年ぐらいの1年生2人、2年生2人の5人も続けて珠算8級に合格です。また、珠算6級の合格者の中では、1年生の女の子3人組が揃って合格です。それもなかなか習得が難しかったわり算の成績がとても良い内容だったのが嬉しいですね。4名いたもう1名も一緒にと思っていましたが年末に引越をしてしまったのが残念でした。さらに6級では、1人、なかなか取れない「300点満点」(学習5か月目の5年生)をとりました。ほか、上級の中では、準1級1人、準2級に5年生の2人と、2年生、3年生が一人ずつ良い成績で合格です。他の上級は、20日の試験場検定の結果がよければなおよいですね。
暗算は、2級に2年生と5年生、3級は受験者がなしで、4級以下は5級で2人が届きませんでしたが、ほかは合格です。今回受験しなかったメンバーと今回の合格者メンバーは次の4月も続けて受験ができそうな内容です。読上算は、3級合格者の3年生はこれで五種3級以上合格に到達です。一方で、2級以上は玉砕、5級はあと10点組多数。4級を含めてもう少し努力が必要です。読上暗算は、2級に2年生が1人合格、3級も1名合格でしたが、1級、4級が玉砕、5級以下は数名はダメでしたが、ほぼ全員が合格でした。読上種目は、少しやり方を変える必要がありそうです。
教室は、今日から「満点チャレンジ(第10回)」です。珠算6級合格者以上の人が、合格級(又は、今回の受験級)に種目別に8分の制限時間で満点(正答率100%)を目指します。「間違えないことへのこだわり、ミスをしない意識を高めるためのもの」ですが、こちらもよい結果がでるかもしれませんね。さらに、来週は前回とても良い成績だった「フラッシュ暗算検定」です。こちらは練習不足の印象もあり、ちょっと心配です。とはいえ、全体としてはレベルアップしているのが見えていますので、結果は楽しみでもありますね。