昨日、6/4(火)に、姉妹校「そろばん日和(びより)」が、東百合丘4丁目の百合ヶ丘コミュニティスペース(百合ヶ丘自治会館)にて予定通り開校しました。地元の自治会さんとのコラボの遠くの教室などには通えない人向けの地域の寺子屋型教室です。初日は、飛び込み入学の2名もあり、4クラス(ジュニアクラスA~C、シニアクラスB)にそろばんははじめての皆さんばかりの年長さんから大人まで10人が初日のカリキュラム(そろばん、算数教材、育脳教材)をこなしました(7月ぐらいからパソコンにも)。ぎこちないはじめてのそろばん利用が少しずつできるようなってきていました。育脳教材にも楽しそうに取り組んでいました。参加された皆さんの感想はどうだったでしょうかね。これから毎週(あるいは隔週)まずは慣れからです。 年長さんのジュニアAに参加した男の子と女の子の2人はすぐに友達になって、終了後も教室、外の縁側を飛び回っていました。元気ですね。「そろばん日和」の教室での実施カリキュラムは本校と同じですが、週2回学ぶ本校の教室と異なるコンパクトな時間が限られる週1回、シニアは月2回の教室ですので、どのように進んでいけるかはまだこれからですね。 *開講日は火曜日のみ。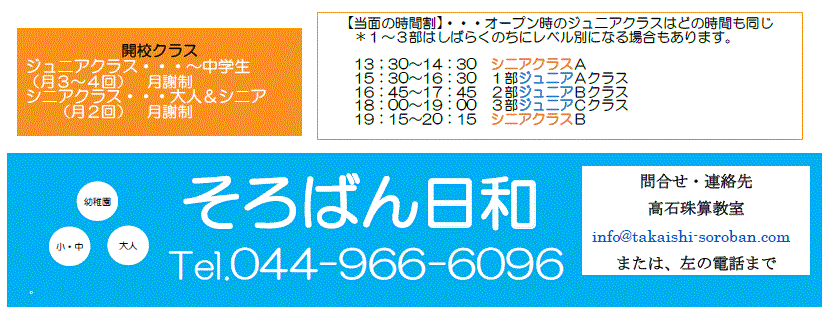
チャレンジ神奈川大会で優勝2つ
昨日5/26(日)、横浜の石川町の会場で、「2024年グランプリジャパン神奈川大会(チャンピオン・チャレンジ)」がチャンピオン33名、チャレンジ237名の申込者で開催されました。教室からは12名(13名申込、1名欠席)が、SIクラスに2名、SⅡクラスに5名、SⅢクラスに5名に参加し、クラス別での腕試しをしてきました。
今年は、参加人数も増えたSⅡとSⅢはレベルがあがってしまいましたが、SⅢクラスの読上算競技、フラッシュ暗算競技で4年生の女の子が優勝できました。トロフィーをいただけます。全体の結果としては、SⅠの「読上算競技1名」、SⅡの「わり算競技1名、みとり算競技1名、読上算競技3名、読上暗算競技2名、フラッシュ暗算競技1名」、SⅢの優勝の2つ以外では、「かけ算競技1名、わり算競技1名、読上算競技2名、読上暗算競技1名」に入賞できました。残念ながら全員の入賞とはできませんでしたが、健闘ですね。来年は会場が川崎に変わる予定です。もっと参加しやすくなりますね。
参加した皆さんは、これだけたくさんの人がいろいろなところで頑張っていることを知ることもでき、また会場大会の雰囲気も経験できたことはとても良い機会だったと思いますがどうですかね。それから、そろばんの会場大会参加のメンバーには、大会で入賞できなくても何が入っているかわかりませんが教室からの追加の「お楽しみ袋」があります。最近は文具やおもちゃなど10個ぐらい入っていることもあり、皆さんとても楽しみにしているようですね。昨日の3部の時間は、川崎会場以外の時は袋は教室渡しなのでの初めて組も3人いたこともあり、「お楽しみ袋」で大いに盛り上がっていました。
運動会と競技会
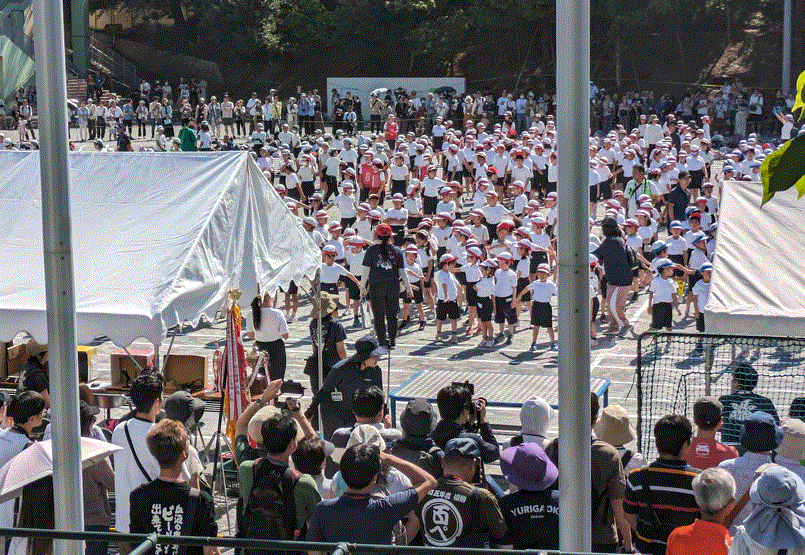
5月には地元の小・中学校で「運動会・スポーツフェスタ」が開催されています。晴天でとても暑かった先週の土曜日に、出身校である小学校に少し時間を見つけて応援に行ってきました。開会式から午前中途中のカリキュラムまで、ダンス、全員でのリレー、ボール転がし、徒競走、玉入れなど、教室には1年生から6年生が教室に習いにきていますが、普段と違った元気な姿を見ることができました。何十年前の卒業ですが、騎馬戦やリレーにでた昔を思い出しますね。
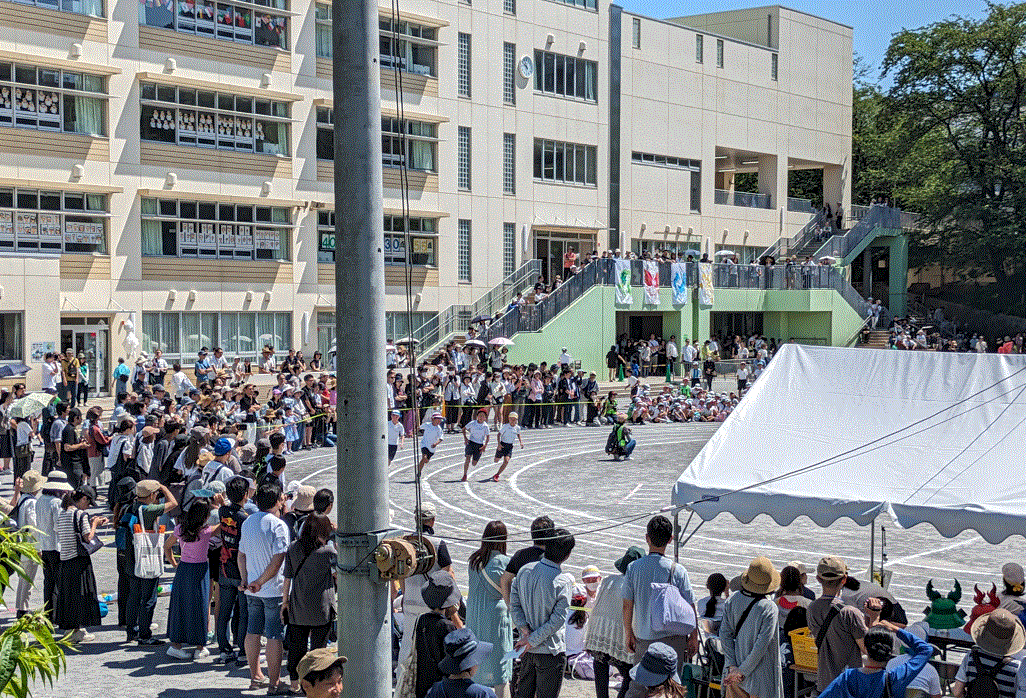

教室では、先週に「第35回全神奈川通信珠算競技大会」を行いました。1週間の期間で欠席者も数名いましたが約50名が参加しました。神奈川県下1600人位の参加者での最終結果は6月になります。前回の11月の大会から半年たっていますので、この期間にどれだけできるようになったかを確認することになります。全員100点以上アップが目標ですが、練習時には10人以上が100点以上アップを出していましたので、本番でしっかりとできたかどうかですね。さらに、今度の5/26の日曜日にはこの通信大会に昨年2回参加したメンバーが参加できる「チャレンジ神奈川大会」が横浜であります。13人が参加予定で、初めての競技会参加者も4人います。今年は少し参加人数が増えたクラスがありますので、入賞できるかどうかはわかりませんが、腕試しともに、楽しんで来てもらえたらと思います。そして、月末は「フラッシュ暗算」の検定週でもあります。40人位が受験予定ですのでしっかりと練習ですね。
姉妹校開校します
先週、先々週に会場になる会館(コミュニティスペース)で体験説明会を開催しました地区自治会とのコラボ企画のそろばん教室「そろばん日和(びより)」を6月からの入会希望者もそろいましたので、来月6月4日より東百合丘4丁目の「百合ヶ丘コミュニティスペース(百合ヶ丘自治会館)」で開校します。高石5丁目の「高石珠算教室」本校の姉妹校となります。地元地域の学童の「読み・書き・そろばん」の町の寺子屋を作り、リテラシー向上を図りたいという地区自治会の方の要望からの開校となります。
開校クラスは2つ(ジュニアクラス、シニアクラス)です。5丁目の教室や新百合、たまプラーザなどのそろばん教室に通うことができない(送迎が難しい、歩いてくることができないなど)「学童(幼児~中学)向けの週1回(月3~4回)学習の教室(ジュニアクラス)」と、そろばんを習ってみたい大人の方や認知症対策&脳トレ希望の「シニア&大人の方向け教室(シニアクラス)」も月2回予定で同時に開校します。基本は毎週火曜日午後(祝日はお休み)に開講し、ジュニアクラスの学習のコンテンツ内容は時間制限がありますが、本校のコンパクト版(算数教材・そろばん一式・育脳教材は利用)」での実施です。シニアクラスの年配者向けは本校で3年前から個別実施の特別カリキュラムの予定です。新規に学習したい大人の方向けはジュニアのそろばん学習と同じです。
当面は、夏休み前ぐらいまで試行錯誤でとなりますが、ゆったりとした広々とした会場での学習ですのでゆっくり進められたらと思っています。パソコンもできるだけ早期に常設予定で、体験説明会にもお見せした脳トレの一つのフラッシュ暗算にも取り組む予定です。もともと本校でも、そろばん技能での能力向上を中心におきますが、さまざまな教材やそろばん種目学習をすることでの能力開発を目的としていますので、「数感覚・計算力だけでなく、集中力・忍耐力・想像力・発想力などのレベルアップ」が本校同様にできればよいですね。
GW中はカレンダー通りです
GW中、教室はカレンダー通りで、祝日はお休みで明日から5/6(月)までお休みで、次は5/8(水)からです。ところで4/29は火曜日で定休日で、狭間の5/1と5/2はお休みが多いかと思いましたが、ふたを開けてみると振替を含めてたくさんの出席でビックリしました。先月4月はここ数年では最多の入学者(新規と転塾者(引越での))があり、教室にも新しいメンバーがそろばん学習に取り組み始めています。タイミング的に2週間後の5/13~教室の8級練習者以上原則全員参加の「第35回全神奈川通信珠算競技大会」の練習にあてました。転塾者にもよい内容で、年2回の競技会ですが、教室では「現状の実力確認と半年間での努力結果を確認する目的で参加」しており、やさしい問題からのピラミッド型の問題に取り組むのは基本理解を含めて本当の実力を確認するにも良い機会ですね。連続参加者は前回比100点アップが目標ですね。
新しく入学の1~2年生は、主に、そろばんと基礎学習練習帳に取り組み始めています。そろばん学習のステップとしては、基本をマスターしてから次は10の合成です。徐々に数感覚がレベルアップしていますので、まずはしっかりと通うことができれば大丈夫です。慣れることと、当たり前の環境が揃っていればですが、周りが同じくらいのメンバーがたくさんで、ほぼ同じ内容を一緒に進める環境となっています。ステップアップも早そうで今後が楽しみですね。3~4年生での新規入学者は基本をマスター後はかけ算九九もほぼ覚えていますので、加速していきます。3~4ヶ月で8級レベルの問題に入れますので、今回のメンバーは8月ごろには検定試験にチャレンジですね。
それから、今月は、以前にも触れましたが(今後どうなるかはまだわかりませんが)、姉妹校を別教室でスタート予定(6月ぐらいからを予定)です。週1回(火曜日)の特別カリキュラムの教室です。地域の方への体験説明会を2回、明日5/4(土・祝)と5/11(土)に行います。ひとつ山を越えたところにある会館でです。こちらの高石の教室まで通うことができない人向けの地域密着型の寺子屋教室で地元の児童の「読み・書き・そろばんのリテラシー向上を図りたい」という地域プロジェクトの方から要望のあったコラボレーション企画です。まずは、10人ぐらいからスタートできればよいかなと今は考えていますがどうでしょうかね。なお、教室名は「そろばん日和(びより)」の予定です。
2024年全川崎珠算競技大会で大健闘!
本日、4/21(日)川崎駅前の川崎商工会議所のKCCIホールにて「 2024年全川崎珠算競技大会 」が開催され、教室からは4・5・6年各2人の計6人の選抜組が腕試しをしてきました。さらに、教室から3年連続参加の6年生の男の子が137名の代表として「選手宣誓」の大役も果たしました。70年以上続く川崎での伝統あるこの大会での大役、よい記念、思い出になりましたね。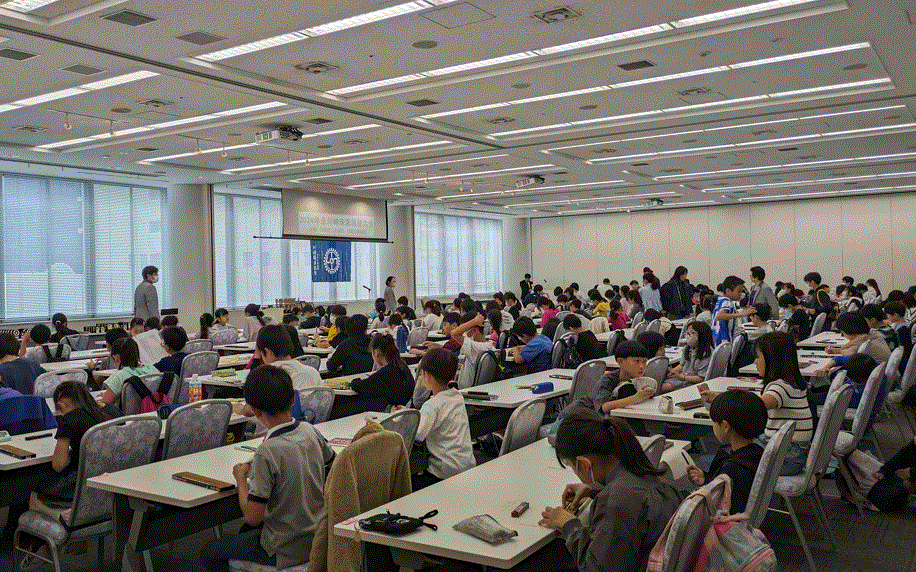
今年の大会全体では137名の申込者で、小学生の部は93名、中学生の部が32名、高校大学一般が12名で、小学生の部では今年も400点満点(小学生は、日商珠算3級問題を「かけ算5分、わり算5分みとり算5分と、暗算1分の計16分」)が4人で同点決勝をするハイレベルな結果の大会でした。通常の日商検定試験の半分の時間という処理スピードと、さらに全問、ひとつも間違えない正確性の高さが要求されるもので、中学生は日商珠算2級、高校大学一般は日商珠算1級に取り組む大会です。中学生の部では満点が出ませんでしたが、高校大学一般の部でも1級問題を1名400点満点でした。素晴らしいですね。
教室の6人の小学生の部に参加の選抜者の成績結果は、今年も大健闘です。激戦の小学生の部、93名の「個人総合競技」の入賞枠に2人(24番目、27番目の点数)、「読上暗算競技」は3人入賞(3位枠に1人、入賞枠に2人)、教室での例年良い結果がでている「読上算競技」では4人入賞(3位枠に2人、入賞枠に2人)、有段者メンバーで臨んだ「フラッシュ暗算競技」も4人入賞(3位枠に3人、入賞枠に1人)できました。普段、種目別については、特に競技会に向けての練習はしていませんので、各自の日々の検定合格を目指した練習で培った技能を競技会で試した結果となります。各自、十分対抗できたという印象だったようで、種目別競技も楽しめたようでなによりでした。このように検定試験だけでなく、こういう競技イベントでもモチベーションが上がるようで選抜者のメンバーにとってはよい経験でしたね。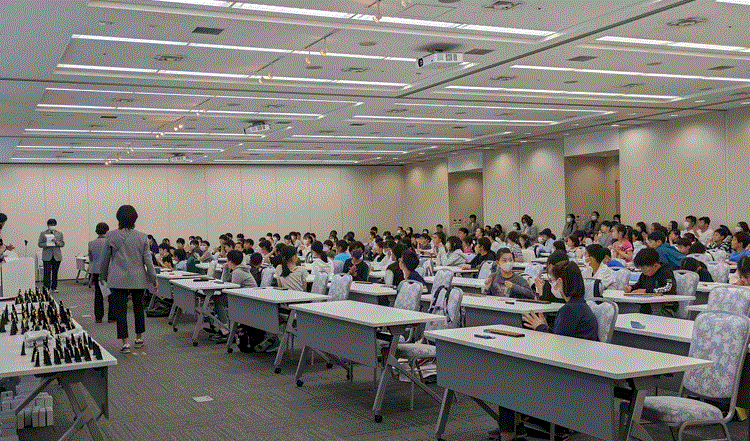
4月教場検定結果(速報)
先週実施の「4月教場検定」の結果を教室のボードに貼り出しました。全体として今回はだいぶ頑張った結果と思います。(珠算11人、暗算13人、読上算14人、読上暗算11人ののべ49人が合格) 4種目の同時受験者はいませんでしたが、3種目同時受験の合格者は2人(4年生、5年生の女の子)でした。今回に5種2級以上合格(来年の3月の表彰式対象者)がかかっていた2人は、読上算2級、読上暗算2級にそれぞれ合格できました。特記事項としては、珠算7級受験の6人、暗算4・5・6級の受験の13人は全員合格です。よく頑張りました。
個別には、「 珠算 」は準1級、準2級に一人ずつ合格です。ただ、5・6級受験者(4級受験者は今回はなし)の2人はあと一歩届かずです。正確性とわり算のレベルアップが必要ですね。7級以下は、先の7級合格者を含めて9人がクリアです。「 暗算 」は先の4級以下の13人はクリアですが、2級以上(3級受験者は今回はなし)は5人とも今回はクリアできませんでした。なかなか難しいかったですね。あと少しですので、次回にリベンジです。「 読上算 」は久しぶりに1級に1人(中3)、2級は3人、3級は1人がクリアできました。4・5・6級は、5級で3人が届きませんでしたが、9人がクリアです。「 読上暗算 」も、久しぶりに1級の合格者が1人(小6)、2級、3級も1人ずつ、4・5級では4人合格、7級は1人がダメでしたが、4人合格です。
そろばんは努力をし続けている人は今回のように検定試験もクリアできていきますね。確かに本番に弱い人もいますが、諦めなければです。教室では、奇数月実施のフラッシュ暗算も含めて5種目、3級以上に合格し、3月の優良生徒表彰式で表彰状、トロフィーや盾をもらうことが一つの目指すべきゴールですね。今回の検定合格でも、2人が新たに対象者になり、あと一つがなかなかの人もいますが、今回であと一種目になった人もいます。「5種(珠算・暗算・読上算・読上暗算・フラッシュ暗算)3級以上合格(日本珠算連盟の5種表彰者)のトータルの技能習得者」になれるように全員が頑張ってほしいですね。6月は日商3級以上検定があります。次の対象者に入れるのは誰でしょうね。
そろばん学習とは?
「電卓、スマホ、パソコンを使う時代にそろばんとは?」多くのみなさんの素朴な疑問ですね。3月に様々な県の特徴を取り上げるTV番組で沖縄県民の若い人も年配者の人も「子供のころのそろばん学習者の今の仕事での活用」の紹介があったり、TVのニュースでも「あんざん能力」がよく取り上げられるテーマですが、そろばんを実際に学んでいる人にとっては実感として「使えると便利な技能」ですね。電卓もスマホもない状態で「頭のなかで計算結果が見えること」は日常生活で十分に役立ちます。技能、能力面ではその点だけでも有益でしょうね。それが今、そろばんを学習する人が増えている理由の一つでしょうね。
今、教室では今週末の検定試験に向けて新1年生から中学生の学習者が練習に励んでいます。なかなか集中して問題に取り組めなかった低学年(1年~4年生ぐらい)の生徒が1年ぐらいで、20分(7級までの試験の制限時間)のそろばん検定の問題にしっかりと止まらずに取り組めるようになってきています。集中して正確に問題に取り組むことができる「集中力」「注意力」、そしてやり方を問題によって正しく当てはめながら問題を解く「判断力」や「論理的思考力」などもどんどんレベルアップしてきています。問題を最後までやり抜く力としての「忍耐力」や検定で失敗しても次にクリアしていく「復活(リベンジ)力」などもですね。これがそろばん学習で身についてくもう一つの面ですね。これもとても大事なものでしょうね。
ところでこのような内容に関連することで、先月3月末に、地元の少し先の自治会さんから「そろばん教室誘致のコラボ企画」のお話がありました。こちらの教室から小山を越えた大人の足で20分ぐらい歩いたところ(子供では30分弱でしょう)の会館でのお話です。まだ一人ではなかなかこちらの教室や新百合ヶ丘、たまプラーザ・あざみ野のそろばん教室などに通うことができない地域の幼児、小学生に向けて「読み・書き・そろばん」などのリテラシーを地元で学習し、高めることが主な目的となっています。さらに、シニア向けの脳トレ、認知症対策トレーニングも別時間(こちらは月2回予定)で実施予定で、6月ぐらいからニーズがあれば、会館の利用可能日とこちらの曜日都合から、週1回(火曜日)でそろばんを学べる企画で動いています。どちらも、こちらの教室で長年実施のコンテンツのコンパクト版企画で、5月前半の祝日、土曜日に体験日を設けており、関連地域でちらしが配布されています。本格的に学習する場合には、複数日通えるそろばん教室の方が技能アップや、習得スピードは速く、おすすめしますが、このような地域企画もよい活動と思いましたのでこのお話を進めています。こういう機会も地域活性化、レベルアップア化の可能性もあり、とても面白いですね。
新年度が始まりました。
そろばんは今日、4/1(月)から新年度、2024年度のスタートです。昨日には、各人のクリアファイルを新学年に交換しています。もう1年たったということですね。学校は今週末、あるいは週明けからのようですが、期変わりは、心機一転、新たな気持ちで取り組んで欲しいと思います。また、今日、明後日の4月はじめからの入学者も3人います。まずは、教室に慣れることからですね。頑張ってみましょう。
既存のメンバーは来週が4月の検定試験となります。今回は、暗算、読上算の受験者が多数です。特に、新3・4年生が一気にレベルアップをはかっていますので、結果をだせるように頑張りましょう。できるようになると面白くなるだけでなく、レベルもどんどんアップしていきますね。何事もそういうものですね。その段階までまずはやってみることが大事ということですね。
ところで、先月3月末、庭の木に巣づくりしていた山鳩の雛が巣立っていきました。2週間ほど手の届く、目の前で、毎日育つことを静かに見ることができていましたが、2羽ともあっという間に大きくなって飛び立っていきました。翌日、帰巣本能があるのかどうかはわかりませんが、庭の木に(恐らくそうだと思いますが)2羽とも1時間ほど戻ってきていました。3月の卒業時期に雛の巣立ちもみれたというのも何かあるようで、面白かったですね。

新年度を迎えるにあたって
教室でも3月での卒業生もいますが、4月から学年が1つ上がります。上の学年に行くにしたがって時間の使い方が大事になりますね。やらなければならないこと、やりたいことも増えてきます。「上手に時間を使うこと」を学ぶことが必要ですね。「タイムマネジメント」をということです。受け身の時間の使い方から主体的、自主的な時間の使い方に変えることがどれだけできるかでしょう。そろばんだけでなくどのような学習も、前向きに努力をすれば必ずステップアップできますが、そうでない場合にはなかなか身につきませんね。大丈夫でしょうか。
さて、教室では4月中旬の「教場検定」、5月中旬の「全神奈川通信珠算競技大会(県通信)」の練習にも入っています。後者は基本をしっかり確認するものです。年に2回の大会に8級以上練習者全員が参加し、半年の学習の成果を確認します。学年は全く関係ありません。珠算3級以上の練習者は、5月の「チャレンジ大会」の選考もです。昨年も優勝のトロフィーを6本もらえた大会です。ほぼ同じレベルの人とのクラス別の競技大会ですので、対象者には伝えていますが、参加希望者は今年も是非頑張ってもらいたいですね。すでに県通信の過去問題で、練習時の結果を自己採点した人は、半年前よりも100点アップ以上もたくさんで、ずいぶんできるようになっていることを得点で実感し喜んでいます。努力は結果としてあらわれているということですね。
また、体験を含めた様々な問い合わせも増えています。「暗算(あんざん)、フラッシュ暗算の学習希望」(もう一つ、読上暗算といういう暗算もありますが)があるのは、今の時代にあっているといえますね。「記憶力」も鍛えられる頭の中で計算する、電卓やそろばんというツールを使わない計算力はやはり時代変わらず「便利で、あったらいいな」の技能なのでしょうね。それをどのレベルまでできるようになるかは努力と時間のかけ方次第です。このコンピュータもスマホも使わずに使える技能は、これからのコンピュータやAIが大きく支配し始めるこれからの時代に、差別化できる人間力を高める一つの重要な能力かもですね。そろばんを「そろばんというツールで計算することというイメージしかない多くの方」には知ってもらいたいことかもですね。
