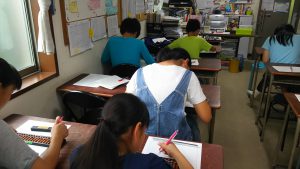この半月ほどは、「 6月検定、満点チャレンジ、あんざんコンクール、フラッシュ暗算検定 」とイベントが続き、検定結果報告以外一つ一つのまとめができていませんでしたが、以下のような結果となっています。初級クラスの1部の時間もほとんどのメンバーが基本を卒業し、今回の競技会などに参加できる人が何人もでてきているなど、短期間で技術レベルを上げ、とてもよく頑張っています。夏休み前後から新たに入学するメンバーがいますので、良い刺激になりますね。そういう意味では、学校に慣れ、夏休みを過ぎるタイミングの例年この時期の9月前後に新たにそろばんをはじめる人も多い地域ですので新たに習い事をお考えの方はご検討いただければと思います。
さて、検定結果と会場実施のあんざんコンクール川崎大会は、以前のコメントの通りですが、教室には5月中旬に実施の「第21回全神奈川通信競技大会(スピード)」の結果が届いています。過去最高の45名が参加し、1000点以上が6名。連続参加者が37名、その中で前回第20回比100点以上アップ者が11名。全体で前回比平均アップが約68点/人。この結果は半年間で多くの人が技量を伸ばし、頑張った結果ですね。また、初参加者が、1年生1名を含み、6名でした。総得点の成績表彰は逃しましたが、過去最高点比較の川崎市内のチャレンジ度表彰(24人)の中で、3人(3年生・4年生・中1生)が表彰されました。毎回、全体のレベルアップになっているようで、次の11月が楽しみですね。
また、試験場検定後に実施の「 満点チャレンジ 」の結果も揃いました。残念ながら、今回も満点はでませんでしたが、合格級の各種目8分ごとの珠算の結果では、種目毎には満点を含め、9割以上の正答率など、一つ下の級での正答率はアップしている人が多数でています。「間違わないことへのこだわり」を是非とも高めてほしいですね。「 全国あんざんコンクール 」の結果も届きました。川崎市内で500名を超える参加者の大会で、教室からは25名が参加できました。結果は、金賞に5名(小3が2名、小6が2名、中3が1名。川崎市内の一覧表に名前記載)、銀賞が13名、銅賞が7名でした。この大会への参加も毎年増えていますので、来年には参加者だけでなく、金賞の入賞者ももう少し増やしたいですね。最後に先週実施の「 フラッシュ暗算検定 」の結果も教室に張り出してあります。中級者は前回のリベンジ組も多数で、7級から10級の1部の初級クラスからの受験者(珠算を初めて1年以内前後)も、合格者多数です。上級者の中では、段位は今回はダメでしたが、あと一歩のメンバーも多く、次回にリベンジですね。